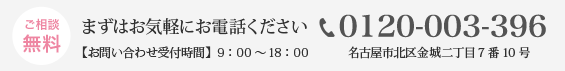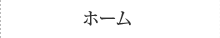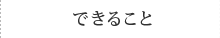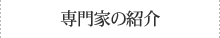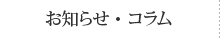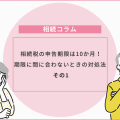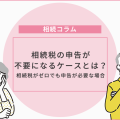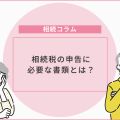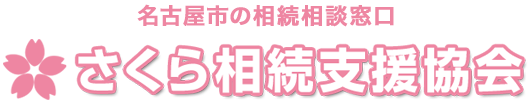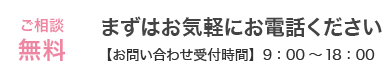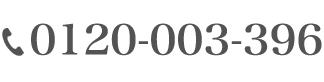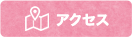相続税が2割加算されるのはなぜ?対象者や注意点をやさしく解説
更新日:2025.11.20
Contents
身近な人以外が財産をもらうと税金が増える?「2割加算」の基本を知ろう!
相続税には、「2割加算」という特別なルールがあります。これは、亡くなった方(被相続人)の配偶者や、子ども・親といった
「ごく近い親族(一親等)」以外の人が、財産を相続したり遺言で受け取ったりした場合に、計算された相続税額に20%が上乗せ
される制度です。
たとえば、孫、兄弟姉妹、甥、姪などがこの対象となり、場合によっては税金の負担が大きく増えることがあります。特に、孫を養子にした場合や、代襲相続(本来相続するはずの人が亡くなっている場合に代わりに相続すること)の場合など、立場によって2割加算の有無が変わる点は注意が必要です。
この記事では、相続税の2割加算が適用される人、仕組み、計算方法、そして税金対策として考えられる生前贈与などについて、わかりやすく解説します。
💰 相続税の2割加算とは
相続や遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)で財産をもらった人には、原則として相続税がかかります。
さらに、その財産をもらった人の中で、亡くなった方との関係が「ごく近い親族」ではない人は、通常の相続税に加えて、その税額の20%分を上乗せして納めなければなりません。これが「相続税の2割加算」と呼ばれるものです。
👥 2割加算の対象者と対象外の人
誰が2割加算の対象となるのか、しっかり確認しておきましょう。
🌟 2割加算の対象となる人
2割加算の対象となるのは、亡くなった方の「一親等(子ども、親)」や「配偶者」ではない人です。
- 兄弟姉妹
- 孫
- 甥、姪
- 内縁関係の配偶者(法律上の夫婦ではないため)
- 友人・知人などの親族ではない人
💡【注意】 内縁関係にある妻(または夫)は法律上の配偶者ではないため、2割加算の対象になります。
🙅 2割加算の対象外となる人
2割加算が適用されないのは、亡くなった方とごく近い親族にあたる、次の人たちです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 養子縁組をした子
- 代襲相続人(代襲相続で財産をもらう孫や甥・姪など)
💡【ポイント】
- 代襲相続人とは、本来の相続人(例:子)がすでに亡くなっている場合に、その人に代わって相続する人(例:孫、甥・姪)のことです。代襲相続人は、本来の相続人と同じ立場になるため、2割加算の対象外になります。
- ただし、孫を養子にした場合は、2割加算の対象になるので特に注意が必要です。(次の項目で詳しく説明します)
孫が相続人になる場合の特に注意すべき点
孫が相続人になる場合、その立場によって2割加算になるかどうかが分かれます。
| 【孫の立場】 | 【2割加算の有無】 | 【理 由】 |
| 養子縁組をした孫 | 加算される | 節税などの目的で養子になった孫は、原則通り2割加算の対象者として扱われるため。 |
| 代襲相続人となった孫 | 加算されない | 親(亡くなった方の子)の代わりに相続するため、親と同じ「一親等」の立場を引き継ぐため。 |
このように、同じ孫でも状況によって取り扱いが変わるため、相続税の計算をする際は間違えないように確認しましょう。
🧐 なぜ2割加算されるのか?理由を解説
2割加算のルールが設けられている主な理由には、税負担の公平性を保つことが挙げられます。
1. 相続の世代飛ばしを防ぐため
例えば、祖父母が遺言で孫に直接財産を渡した場合、「祖父母→子→孫」と世代を追って相続する通常の流れよりも、相続の回数が1回少なくなります。その分、本来かかるはずだった相続税を回避したことになってしまい、税金の負担が少なくなってしまいます。
2割加算は、このような**「世代飛ばし」によって税負担が軽くなることに対する調整**の役割を担っています。
2. 経済的な影響の少なさへの配慮
配偶者や子、親といったごく近い親族は、亡くなったことで生活に経済的な影響が出ることが多いと考えられます。しかし、兄弟姉妹や甥・姪といった遠い親族や親族外の人は、**「思わぬ財産」**を得たという側面が強くなります。
亡くなった方に近い親族との税負担の公平性を保つため、関係性の遠い人に対しては税額を20%加算していると言えます。
🔢 相続税と2割加算の計算例
2割加算の計算は、まず通常の相続税額を算出した後に行います。
相続税の計算の簡単な流れ
- 「正味の遺産額」から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、相続税の対象となる遺産総額を計算する。
- 遺産総額を、いったん法定相続分(民法で決められた分け方)で分け、それをもとに各相続人の相続税を計算し、**合計額(相続税の総額)**を求める。
- 相続税の総額を、実際に相続した財産の割合に応じて分け、各人が納める相続税額を算出する。
2割加算の計算例
上記の計算で、養子となった孫の通常の相続税額が100万円だったとします。
- 2割加算額:100万円 × 20% = 20万円
- 最終的な納税額:100万円 + 20万円 = 120万円
⚠️ 【重要】 2割加算は、控除(差し引き)をする前の相続税額で計算されます。
🛡️ 2割加算の対策として生前贈与も検討しよう
相続税の2割加算への対策として、生前贈与(生きているうちに財産を贈ること)という方法があります。
🎁 孫への生前贈与は有効な対策に
- 年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません(暦年贈与の基礎控除)。
- 贈与には贈与税がかかりますが、教育資金の一括贈与の特例など、非課税で贈与できる特例もあります。
- 相続税には、亡くなる前の一定期間内に行った相続人への贈与を、相続財産に含める**「持ち戻し」**というルールがあります。
- しかし、法定相続人ではない孫への贈与は、この「持ち戻し」の対象外です。
つまり、相続税対策としては、孫などの法定相続人ではない人への生前贈与が有効な手段の一つとなります。
⚠️ 【注意】 養子縁組などで法定相続人となった孫は、この「持ち戻し」の対象になるため注意が必要です。相続対策で孫を養子にする場合は、生前贈与を活用した方が有利なケースもあるため、専門家への相談をおすすめします。
さいごに:もしもの時の注意点
相続税の2割加算は、配偶者やごく近い親族(一親等)以外の人が財産をもらうと適用されるルールです。
- 孫を養子にしても、孫の相続税の2割加算は適用されるため注意が必要です。
- 2割加算の対象者が相続放棄をした場合でも、生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)を受け取った場合は、その税金に2割加算されます。
2割加算を適用せずに申告すると、ペナルティ(加算税や延滞税)を受ける恐れがあります。
申告に不安がある場合は、相続税に詳しい税理士に相談するようにしましょう。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
電話 0120-003-396
お問合せ受付時間 平日9時から18時
名古屋市の税理士法人アイフロント