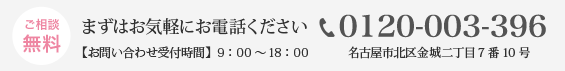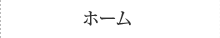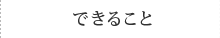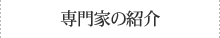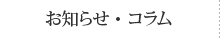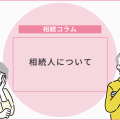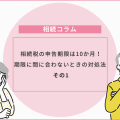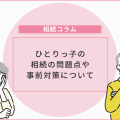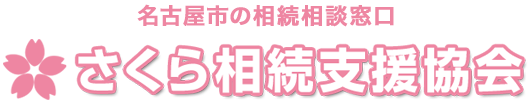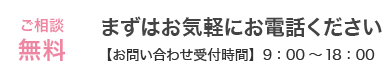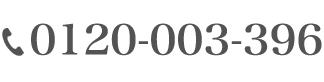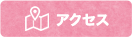相続税の対策には生命保険が有効!対策内容や注意点について解説!
更新日:2024.06.06
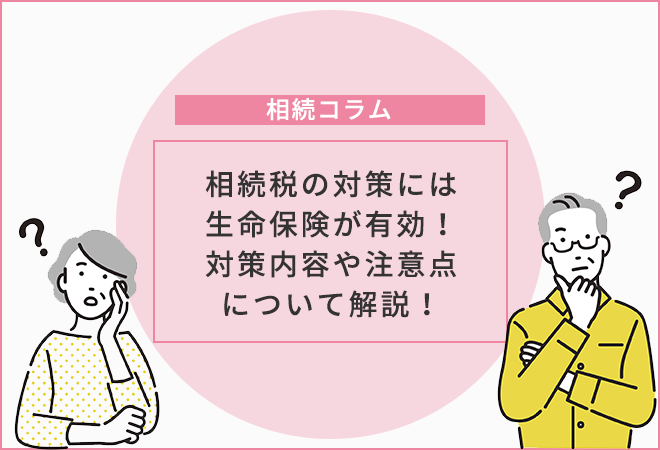
相続税対策に生命保険を活用するといいとよく聞きますよね。
しかし、なぜいいのか、どのようにして対策になるのかきちんと理解できているでしょうか。
単に生命保険に加入すれば対策になると思っていると、思わぬ落とし穴に落ちるかも知れません。
この記事では、相続税対策をお考えの方へ向けて、生命保険が相続税対策になる理由について解説します。
生命保険を活用する際の注意点なども説明しますので、参考にしてください。
Contents
なぜ生命保険が相続税対策になるのか
生命保険が相続税の対策となる理由は、相続税の非課税枠が利用できるためです。
被相続人(亡くなった方)が契約していた生命保険金を受け取ると、相続税がかかります。
このとき、相続人には生命保険の非課税枠が適用されるので、非課税枠分を受け取り額から差し引けます。
非課税枠は、相続人の生活を支えるという側面が生命保険にはあることから、設けられたものです。
生命保険の非課税枠は以下の計算で求めます。
【500万×法定相続人の数】
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人であった場合、【500万×3人】で非課税枠は1,500万円です。
法定相続人の数には相続放棄を行った人も含まれ、上記の例で子どものうち1人が相続放棄をしていても、非課税枠は変わりません。
各受取人の控除額は保険金額に応じて変わる
生命保険を複数の相続人が受け取った場合の、各受取人の控除額の計算方法は以下の通りです。
(その相続人が受け取った生命保険金の金額)
▲ 非課税限度額 × (その相続人が受け取った生命保険金の金額) / (すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額)
例として、配偶者と子ども2人が生命保険金を受け取った場合で考えてみましょう。
生命保険金を配偶者が2,000万、子どもそれぞれが1,000万ずつ受け取ったとします。
この場合の非課税限度額は【500万×3人=1,500万】です。
次に相続人それぞれの課税額を計算します。
配偶者
2,000万-1,500万×2,000万÷4,000万=1,250
子ども
1,000万-1,500万×1,000万÷4,000万=625
配偶者は750万円、子どもそれぞれは375万が非課税となりました。
ただし、ここで計算した課税額に相続税がそのままかかるわけではありません。
非課税額を超えた部分の生命保険金は、他の財産と合算して相続税を計算します。
そのため、他の財産と合わせた課税財産が相続税の基礎控除額を超えない場合は、相続税は発生しません。
節税には受取人を誰にするかが重要
相続税の対策で生命保険を活用するには、保険金の受取人を誰にするのかが重要です。
選択によっては、保険金での相続税対策の効果を十分に得られない可能性もあります。
下記にて配偶者、子、孫を受取人にした場合のポイントについて説明します。
配偶者の場合
配偶者には「配偶者の税額の軽減」という、相続税を大幅に軽減する制度が適用されます。
配偶者が取得した相続財産が、次のうちどちらか多い方の額まで配偶者は相続税がかかりません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者は最低でも1億6千万円までは非課税になるため、生命保険の非課税枠が必要ないケースも多くあります。
子の場合
子の場合は、配偶者のような税金軽減の制度はないので、生命保険の控除は大きな節税ポイントになります。
父母と子ども2人の家族で相続税のシミュレーションをしてみましょう。
父が1億5千万の財産をもっていたとします。そのうち1,500万円分は生命保険で受け取る予定です。
<母を生命保険の受取人とした場合>
母の受け取る財産:6,000万(生命保険1,500万円分は非課税なので含めず)
子1の受け取る財産:3,750万
子2の受け取る財産:3,750万
相続財産の合計:1億3,500万(※生命保険は非課税枠内のため除外)
相続税の基礎控除額:4,800万
課税価額:8,700万
母の税金:8,700÷2=4,350万 4,350×20%-200=670万
子の税金:8,700÷4=2,175万 (2,175×15%-50)×2=552万
相続税の総額:670+552=1,222万
母の納税額:1億6千万円以下なので納税0
子の納税額:1,222÷8,700×3,750=526万
<子2人を受取人にした場合>
母の受け取る財産:7500万
子1の受け取る財産:3,000万(生命保険750万円分は非課税なので含めず)
子2の受け取る財産:3,000万(生命保険750万円分は非課税なので含めず)
相続財産の合計:1億3,500万(※生命保険は非課税枠内のため除外)
相続税の基礎控除額:4,800万
課税価額:8,700万
母の税金:8,700÷2=4,350万 4,350×20%-200=670万
子の税金:8,700÷4=2,175万 (2,175×15%-50)×2=552万
相続税の総額:670+552=1,222万
母の納税額:1億6千万円以下なので納税0
子の納税額:1,222÷8,700×3,000=421万
配偶者を生命保険の受取人にした場合と、子どもを受取人にした場合で相続税額に200万円以上の差が出ました。
相続税対策で生命保険を活用するなら、税優遇がある配偶者ではなく子どもを受取人とするのがおすすめです。
孫の場合
生命保険金の受取人を孫にすると、相続税対策どころか、余計税金が高くなります。
なぜなら、孫は相続人ではないためです。
生命保険金の非課税枠を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人が保険金を負担していた
- 受取人が相続人である
相続人とは法定相続人のことを指し、孫は法定相続人ではないため非課税枠の適用は受けられません。
孫が法定相続人となるのは、被相続人よりも前に子が亡くなった場合(代襲相続)や、孫を養子縁組した場合です。
こうした事情がない限り孫は相続人とはならず、生命保険の非課税枠も使えません。
さらに、被相続人の配偶者や被相続人の一親等の血族(子や親)以外の相続税は、本来の相続税の2割増しとなります。
これらのことから、生命保険金の受取人を孫とすることは、相続税対策にはならないと言えます。
相続税対策に生命保険を活用するメリット
相続税対策に生命保険を活用するメリットは、主に以下の3点です。
- 非課税枠が使える
- 納税資金として使える
- 財産を残したい人に渡せる
具体的に見ていきましょう。
非課税枠が使える
第一に、【500万円×法定相続人の数】分の非課税枠があるという点です。
生命保険金を1人で受け取る場合にも、非課税枠全てを活用できます。
納税資金として使える
生命保険金は、銀行口座のように凍結されることがありません。
例えば遺産分割協議が整わず、一旦法定相続分で申告納税することになった際や、相続財産に不動産が多い場合に納税資金として使えます。
相続税の納税は原則現金での一括払いですので、納税資金を用意できるというのは大きなメリットです。
財産を残したい人に渡せる
生命保険では受取人を指定できるため、財産を残したい人に確実に残せます。
相続させる人を指定する方法として、遺言書で明記する方法もあります。
しかし、相続人には遺言でも奪えない遺留分という権利があるため、被相続人が願う通りに財産を残せるとは限りません。
この点、生命保険は受取人固有の財産となるため、遺留分の請求を受ける心配もなく財産を残せます。
生命保険を相続税対策にする際の注意点
相続税対策で生命保険を活用する際に注意すべき点について、説明します。
非課税枠は相続人しか使えない
先にも説明した通り、生命保険の非課税枠は相続人しか使えません。よって、孫や相続人以外の親戚も適用外となります。
また、相続放棄をした相続人も生命保険金を受け取れますが、非課税枠は使えないことにも注意が必要です。
相続税対策に適した保険選びも重要
生命保険には定期保険、養老保険、終身保険があります。
定期保険や養老保険は期間が定められているため、いつ生じるかわからない相続税対策には向いていないでしょう。
相続税対策に保険を活用するのであれば、終身保険の検討がおすすめです。
さいごに
生命保険を活用した相続税対策について説明しました。
生命保険の活用は相続税対策はもちろん、納税資金を準備できるといったメリットもあります。
しかし、受取人を誰にするかで相続税対策の効果に大きな差が生じるため、慎重に考えることが必要です。
相続税対策は税制や特例なども関係し、大変複雑です。
生命保険の活用も、ひとつ間違えばかえって税負担が重くなることもありますので、税理士法人アイフロントにご相談ください。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
名古屋市の税理士法人アイフロント
名古屋オフィス – 名古屋市北区の税理士事務所 |税理士法人アイフロント (ai-front.com)