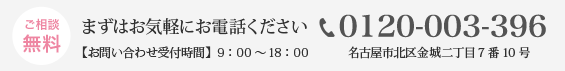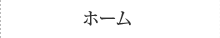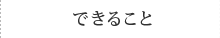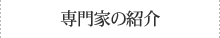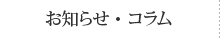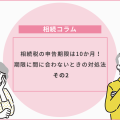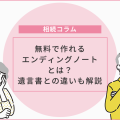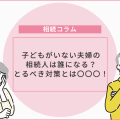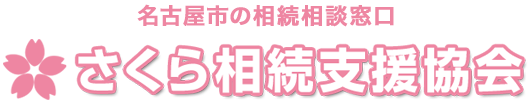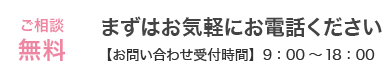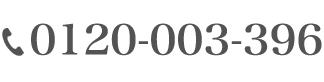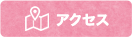相続税の申告をサボるとどうなるの?税務署の調査や厳しいペナルティについて解説!
更新日:2025.07.25
Contents
はじめに
もし、家族が亡くなって財産を受け継ぐことになった時、「相続税」という税金を国に払わなきゃいけないことがあります。でも、「めんどくさいから」「知らないふりしとこう」って申告をしないままでいると、後で国(税務署)に見つかって、すっごく厳しいペナルティを受けることになっちゃいます。
さらに、本来なら税金が安くなる「お得な制度」も使えなくなって、結局もっとたくさんの税金を払うハメになることも…。
この記事では、どうして申告してないことがバレるのか、どんなお仕置きがあるのか、そしてもし申告が間に合わなかったらどうすればいいのかを分かりやすく説明していくね!
相続税の申告をサボるとどうなるの?
相続税の申告をしないでいると、本当に大変なことになります。でも、みんながみんな相続税を払わなきゃいけないわけじゃないよ。相続税がかかるのは、もらった財産が「基礎控除額」っていう金額よりも多かった場合だけなんだ。
基礎控除額は、【3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数】 で計算できるよ。
例えば、相続人が一人なら3,600万円、二人なら4,200万円までなら税金はかからないってことだね。
もし、もらった遺産がこの基礎控除額より多い場合は、亡くなったことを知った日の次の日から10か月以内に、相続税の計算をして国に申告して、税金を払う必要があります。相続税は、もらった人たちが自分で税金を計算して申告しなきゃいけないんだ。
じゃあ、なんで国は申告してないことが分かるんだろう?そして、もしバレたらどうなるんだろう?これから詳しく見ていこう!
申告してないことや申告ミスは、税務署の調査でバレる!
市役所に誰かが亡くなったことを知らせる「死亡届」を出すと、市役所はその情報を税務署に連絡するルールになっています。その時、亡くなった人が持っていた土地や家の情報も一緒に税務署に送られるんだ。
それに、日本の税務署や国税庁は、「国税総合管理(KSK)システム」っていうすごいシステムでつながっていて、個人のこれまでの税金の申告内容や、いつ税金を払ったかなどの情報を全部知ることができるんだ。
だから、市役所からの情報とKSKシステムを組み合わせると、「あれ?この人、財産がありそうなのに相続税の申告をしてないぞ?」ってすぐに怪しい人を見つけ出して、さらに詳しく調べ始めることになるんだね。
もし申告していないことが疑われて「税務調査」が入ることになったら、税務署はすごく強い権限を使って、銀行や証券会社の口座も調べることができます。その時は、亡くなった人自身の口座だけでなく、財産を受け取ったと思われる家族の口座も調べられるよ。
じゃあ、「銀行に預けないで、家の中に現金を隠しておけば見つからないでしょ?」って思う人もいるかもしれないね。でも、残念ながら、いわゆる「タンス預金」も、だいたい見つかります。税務署の人たちは、調査のプロだからね。ちょっとでもおかしな点があれば、徹底的に調べられます。「黙っていれば分からないだろう」なんて考えるのは、かなり危険な考え方だよ。
申告しないと、税金が安くなる制度が使えなくなる!
相続税には、財産を受け継ぐ人の負担を軽くしたり、その後の生活を守ったりするために、いろんな「税金が安くなるお得な制度(優遇措置)」があります。
例えば、配偶者(夫や妻)が相続する時に1億6,000万円まで税金がかからなくなる「配偶者の税額軽減制度」や、家の敷地の評価額を最大80%も安くできる「小規模宅地等の特例」などだね。
これらの優遇措置や特例は、ちゃんと申告することが条件になっていることが多いんです。だから、もし申告をしなかったら、せっかくお得な制度があっても使うことができません。もし、これらの制度を使って計算した結果、税金が全くかからなかったとしても、申告は絶対に必要なんだ。本当に申告しなくていいのか、しっかり確認することが大切だよ。
申告しないと、厳しいペナルティが増える!
相続税の申告が必要なのに、それをしなかった場合、本来払うべき税金に加えて、さらに「ペナルティ」が上乗せされます。このペナルティの金額は、申告期限をどれくらい過ぎたか、悪質なのかどうか、自分で「やっちゃった!」って気づいて申告したかどうかで変わってきます。一つだけでなく、いくつものペナルティを受けることも珍しくありません。
国税庁の発表によると、2022年度(令和4年度)に追徴された税金(本来の税金に加えてペナルティとして徴収された税金)は、なんと111億円!これは2009年度(平成21年度)以降で過去最高なんだ。これは、税務署が「申告してない人がいると不公平だ!」と考えて、調査に力を入れている証拠だね。
相続税の申告をサボるとどんなペナルティがあるの?
申告しなかったり、本当の金額よりも少なくごまかして申告したりすると、次の4つのペナルティが上乗せされます。
- 延滞税(えんたいぜい)
- 無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
- 過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
- 重加算税(じゅうかさんぜい)
具体的にどんな内容か見ていこう!
延滞税(えんたいぜい)
これは、税金を決められた期日までに払わなかった場合に上乗せされる税金です。税金を払う期限の次の日から、実際に払う日までの日数に応じて、利息のように増えていきます。
延滞税の割合は、次の2つの期間で変わります。
- 期限の次の日から2か月以内:年7.3%と「延滞税特例基準割合(※後で説明)」に1%を足した割合の、低い方が適用されます。
- 期限の次の日から2か月を過ぎた後:年14.6%と「延滞税特例基準割合」に7.3%を足した割合の、低い方が適用されます。
※「延滞税特例基準割合」は、毎年変わる銀行の金利などによって計算されます。
例えば、2024年(令和6年)だと、こんな割合だよ。
見てわかるように、期限を2か月以上過ぎると、延滞税の割合がかなり高くなるから注意が必要です!
無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
これは、決められた期限までに申告をしなかった場合で、ちゃんと申告しなかった理由がない時にかかる税金です。払うべき税金の額によって、上乗せされる割合が変わります。
※2024年1月1日以降に申告期限がくるものの場合
ただし、税務署に調べられる前に「しまった!」と思って自分で期限を過ぎてから申告した場合は、上乗せされる割合が少し安くなります。
※2024年1月1日以降に申告期限がくるものの場合(自分で申告した場合)
さらに、次の条件をすべて満たせば、期限を過ぎて申告しても無申告加算税がかからないこともあります。
- 期限を過ぎてから1か月以内に、自分で申告したこと。
- 元々、期限内に申告するつもりだったと認められる特別な場合であること。
- これは、次の両方に当てはまる場合を言います。
- その遅れての申告で払うべき税金の全額を、税金を払う期限までに払っていること。
- その遅れての申告書を提出した日からさかのぼって5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、かつ、これまでも「期限内申告するつもりだったと認められる場合」として無申告加算税を免除されたことがないこと。
- これは、次の両方に当てはまる場合を言います。
でも、「遺産をどう分けるか、家族で話し合いが終わらなかったから申告しなかった」というのは、「正当な理由」にはならないので気を付けてくださいね!
過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
これは、本当はこれだけ払わなきゃいけないのに、少なくごまかして申告した場合にかかる税金です。本来の税金との差額に対して上乗せされます。
もし、申告の間違いに自分で気づいて、税務署に調べられる前に正しい金額に直して申告し、差額の税金を払えば、この過少申告加算税はかかりません。でも、税務署から「これから調査しますよ」という連絡が来たり、実際に調査されたりした後だと、次の割合が上乗せされます。
申告した後で新しい財産が見つかったなど、申告内容を直す必要があるときは、できるだけ早く直して申告し、税金を払いましょう。
重加算税(じゅうかさんぜい)
ペナルティの中で一番重いのが、この重加算税です。これは、わざと申告内容をごまかしたり、財産を隠したりするような、とても悪質な場合に適用されます。
上乗せされる割合は次のとおりです。
- 申告しなかった場合:追加で払う税金の40%
- 申告したけど金額が少なかった場合:追加で払う税金の35%
さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は、上記の割合に加えてさらに10%上乗せされます。
もし、申告しなかったことや、申告した金額が正しくなかったことに悪意がなければ、無申告加算税や過少申告加算税がかかることになります。
相続税の申告は、ミスなく遅れずに行うことが大切!
できるだけ間違えずに、そして期限内に申告と納税を済ませられるように、よくあるミスや、もし期限に間に合わなかった場合の対処法について紹介します。
生前にもらったプレゼント(生前贈与)の漏れに注意!
相続税を計算するときには、亡くなった人が生前に家族にプレゼントしていたもの(「生前贈与」といいます)も、一部相続財産に含めて計算しなければなりません。
2023年(令和5年)中に行われた贈与までは、亡くなる前の3年間の贈与が対象になります。2024年(令和6年)以降は、亡くなる前の7年間の贈与が対象になるから注意が必要です。
たとえ毎年110万円以下で贈与税がかからないようなプレゼントだったとしても、相続財産に含めて計算する必要があるんだ。
また、特別な制度で、最大2,500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」という制度を利用していた場合も、同じように相続財産に含めて計算しなければなりません。ただし、相続時精算課税を使っていた場合は、毎年110万円以下の金額は含めなくて大丈夫です。もし、相続時精算課税制度で、すでに贈与税を払っているお金があれば、その税金は後で返してもらうこともできます。
生前にもらったプレゼントは、相続財産に含めるのを忘れがちなので、過少申告加算税や延滞税がかからないように、しっかり確認しましょう。
<確認するポイント>
- 自分が生前にもらったプレゼントを、相続財産に含めるべきか確認する。
- 「相続時精算課税制度」を使っていたら、毎年110万円を超える部分を相続財産に含める。
特別な事情がある場合は、申告期限を延ばせることも!
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の次の日から10か月以内にしなければなりません。
でも、地震や大雨などの「自然災害」で被害を受けたなど、本当に「特別な事情」がある場合は、申告期限を延ばしてもらうことができます。もし期限の延長を申請する場合は、事前に、または申告書と一緒に、自分の住所を管轄する税務署に申請書を出しましょう。
災害などではなく、「家族で遺産の分け方について話し合いが終わらなかった」といった理由では、残念ながら期限の延長は認められません。
もし申告期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、とりあえずは遺産が法定相続分(法律で決められた分け方)で分かれたと仮定して、一旦申告と納税を済ませます。その時、「3年以内の分割見込書」という書類を申告書と一緒に提出しておきましょう。
本来、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といったお得な制度は、遺産がちゃんと分けられていないと使えません。でも、「3年以内の分割見込書」を出しておくことで、後で遺産が分けられた時に、これらの特例を使うことができるんです。さらに、無申告加算税や延滞税といったペナルティを受ける心配もありません。申告期限を過ぎることのリスクはとても大きいので、間に合わないからといって諦めず、税理士さんや税務署に相談することが大切です。
相続税の申告は、相続に詳しい税理士さんに頼もう!
相続税の申告をしないとどうなるのかについて説明しました。国は、「税金はみんなで公平に払おうね」という考えなので、申告しない人への対応はどんどん厳しくなっています。「黙っていればバレないだろう」なんて考えていると、本来払うべき税金よりも、はるかに多い税金を払うことになるかもしれません。
相続税の計算や手続きは複雑なので、少しでも不安な場合は、相続について詳しい税理士さんに相談することをおすすめします。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
電話 0120-003-396
お問合せ受付時間 平日9時から18時
名古屋市の税理士法人アイフロント
名古屋オフィス – 名古屋市北区の税理士事務所 |税理士法人アイフロント (ai-front.com)