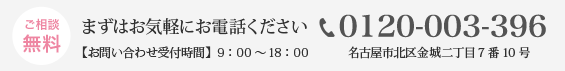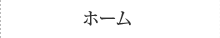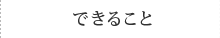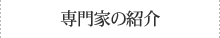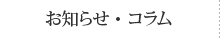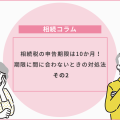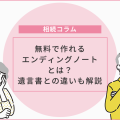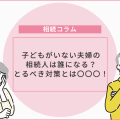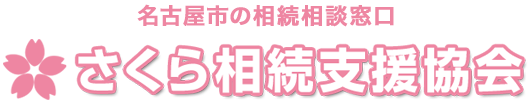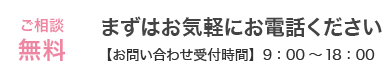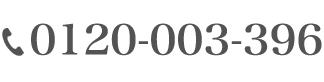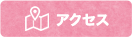「おしどり贈与」って何?夫婦で家をプレゼントし合う、お得なワザ!
更新日:2025.08.09
Contents
はじめに
「おしどり贈与」って言葉、聞いたことありますか?これは、夫婦の間だけで使える、ちょっと特別なプレゼントのルールなんです。特に、住んでいる家や、家を買うためのお金をプレゼントするときに使うと、普通ならかかる「贈与税」という税金が、なんと最大2,110万円までタダになっちゃう、すごく便利な制度なんです!
でも、この制度を使うにはいくつか条件があって、場合によっては、あとでかかる「相続税」という別の税金を安くする効果があまりないこともあります。
この記事では、「おしどり贈与」がどんなもので、どんな時に使えて、どんなメリットや注意点があるのかを分かりやすく説明していきますね!
おしどり贈与ってどんな制度?
「おしどり贈与」の正式な名前は「贈与税の配偶者控除」といいます。 贈与税には、誰にでも適用される「年間110万円までなら税金がかからない」という基本的なルールがあります。 それに加えて、この「おしどり贈与」を使うと、夫婦の間で2,000万円まで税金がかからなくなります。
つまり、この二つのルールを合わせると、
合計で2,110万円まで、夫婦の間で家やそのお金をプレゼントしても税金がかからない
ということになります。 すごくお得ですよね!
おしどり贈与が使える条件
「おしどり贈与」を使うには、次の3つの条件を全部クリアする必要があります。
- プレゼントするものが「住むための家」か「家を買うためのお金」であること
- この制度は、あくまで住むための家や、家を買うためのお金にしか使えません。車や株など、他のものをプレゼントするときには使えないんです。
- 結婚して「20年以上」たっている夫婦であること
- この制度は、結婚して20年以上経っている夫婦だけが使えます。まだ結婚して日が浅い夫婦や、籍を入れていないカップル(内縁関係)は使えません。 もし一度離婚して、また同じ人と再婚した場合でも、結婚していた期間を合計して20年以上になれば大丈夫です。
- プレゼントされた家(または買った家)に「今も住んでいて、これからもずっと住み続けること」
- プレゼントされた家(または買った家)に、実際に今も住んでいて、これからもずっと住み続ける予定であることが条件です。 旅行で使う別荘などは、「住むための家」には入りません。 また、「これからも住み続ける」というのは、贈与した時点で決まります。なので、「将来、この家を売るかもな~」と思っている場合は、この制度は使えないんです。
おしどり贈与のいいところ(メリット)
じゃあ、具体的に「おしどり贈与」を使うとどんな良いことがあるのでしょうか?主なメリットは次の4つです。
- 将来の「相続税」が安くなるかも?
- 家をプレゼントすることで、家を贈った人(夫や妻)の財産が減ります。そうすると、将来その人が亡くなった時にかかる「相続税」が安くなる可能性があります。 例えば、お父さんの財産が家を含めて5,000万円あって、お母さんと子供1人が相続する場合を考えてみましょう。もし家(評価額1,800万円)を先にお母さんに贈与しておけば、お父さんの財産が減るので、相続税の基本的な控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)内に収まって、相続税がかからなくなる可能性があります。
- 亡くなる直前のプレゼントでも大丈夫!
- 普通は、亡くなる前の7年以内に行ったプレゼントは、相続財産に含めて相続税を計算しなければなりません。 でも、「おしどり贈与」の場合は特別で、亡くなる直前に行っても、相続財産に含めなくていいんです。 だから、「いつ贈与しようかな?」と心配せずに、いつでもプレゼントすることができます。
- 残された家族(配偶者)が、住む家に困らなくなる!
もし夫や妻が亡くなってしまっても、事前に「おしどり贈与」で家の名義を変えておけば、残された家族は住む場所に困る心配がなくなります。 これは、とても大きな安心感になりますよね。
- 将来、家を売るときに税金が安くなるかも!
- 「おしどり贈与」で家をプレゼントした後も、ずっと住み続ける予定だったとしても、将来、家を売る必要が出てくるかもしれません。そんな時、「マイホームを売った時の3,000万円特別控除」という制度が使えます。 これは、家を売って得た利益から、最大3,000万円を引いて税金を計算できるというものです。 もし夫から妻に家の半分を贈与しておけば、売却が必要になった時に、夫と妻それぞれにこの特例が使えるので、それぞれ3,000万円、合計で最大6,000万円まで控除できる可能性があります。
おしどり贈与の注意点(デメリット)
「おしどり贈与」には、気をつけたい点もいくつかあります。 次の3つのデメリットも知っておきましょう。
- 相続税対策にならない場合もある
- 相続の時には、「小規模宅地等の特例」という、家の敷地の評価額を大きく下げられる特別なルールがあります。 この特例を使うと、家の敷地の評価額を最大80%も安くできるんです。 例えば、評価額が2,000万円の土地でも、この特例を使えば400万円まで評価額を下げられます。 「おしどり贈与」を行っても、この特例を使った場合と比べると、相続税を安くする効果が少ない場合があります。 後で説明する諸費用も考えると、さらに節税効果が小さくなることもあります。
- 家をプレゼントするときは、相続よりお金がかかる
- 「おしどり贈与」で家をプレゼントすると、「不動産取得税」と「登録免許税」という税金がかかります。 不動産取得税:これは家をプレゼントされた人が払う税金で、家の固定資産税評価額の4%かかります。 相続で家をもらった場合は、この税金はかかりません。 登録免許税:これは家の名義を変える時にかかる税金です。相続の場合もかかりますが、その税率は0.4%です。 でも、「おしどり贈与」の場合は2%かかるので、相続で家をもらう方が、この税金は安くなります。
- プレゼントされた人が先に亡くなる可能性も
- 「おしどり贈与」で家をプレゼントしても、プレゼントされた配偶者の方が先に亡くなってしまう可能性もあります。 もし子供や他の家族がいる場合は、財産が引き継がれるので全く無駄になるわけではありません。 でも、夫婦二人だけの世帯だと、せっかく「おしどり贈与」にかけた費用がムダな出費になってしまうこともあるので、よく考えてから決める必要があります。
おしどり贈与の手続き
「おしどり贈与」を使うには、次の3つの手続きが必要です。
-
プレゼントの約束をする(贈与契約)
まず、夫婦間で「家をプレゼントします」「はい、もらいます」という約束をします。口約束でも大丈夫ですが、後で「言った」「言わない」のトラブルにならないように、書面に残しておくのがおすすめです。「贈与契約書」という書類を作っておくと良いでしょう。
-
家の名義を変える(不動産登記)
約束ができたら、法務局という役所で家の名義を変える手続きをします。この手続きには、贈与契約書や家の権利証、印鑑証明書など、いくつかの書類が必要です。 もし手続きが不安なら、司法書士という専門家にお願いすると安心です。
-
贈与税の申告をする
「おしどり贈与」を使って家をプレゼントされた人は、「贈与税の申告」という手続きをしなければなりません。たとえ税金が0円だったとしても、申告は必要です。 申告は、プレゼントされた年の翌年の3月15日までに、自分の住所がある地域の税務署で行います。 贈与税の計算や申告の仕方が心配なら、税理士という専門家に相談してみてください。
おしどり贈与でよくある質問
ここからは、「おしどり贈与」について、よくある疑問に答えていきますね。大事な注意点もあるので、参考にしてください。
-
「おしどり贈与」は何回でも使えるの?
同じ配偶者からの「おしどり贈与」は、人生で1回しか使えません。 たとえ離婚して同じ人と再婚しても、使えるのは1回だけです。 でも、もし別の相手と再婚して、その人との結婚期間が20年以上になれば、また「おしどり贈与」が使える可能性があります。
-
別居していても「おしどり贈与」は使える?
「おしどり贈与」の条件には、「結婚期間が20年以上」というのはありますが、「一緒に住んでいること」という条件はありません。 だから、別居していても、結婚期間が20年以上であれば「おしどり贈与」は使えます。
-
「おしどり贈与」の後に離婚しちゃっても大丈夫?
「おしどり贈与」は、家をプレゼントした時に夫婦であれば条件を満たします。 なので、贈与が終わった後に離婚したとしても、その贈与が無効になることはありません。
-
お金を贈与して住宅ローンを返済した場合は「おしどり贈与」が使える?
この場合は、「おしどり贈与」が使えない可能性が高いです。 例えば、夫が100%所有している家の住宅ローンを、妻が夫にお金を贈与して返済したとします。 「おしどり贈与」は、「家を手に入れるため」の贈与が対象です。 住宅ローンによって夫はすでに家を手に入れているので、妻からのお金の贈与は「家を手に入れるため」とは言えないでしょう。 なので、このケースでは「おしどり贈与」は適用されないと考えられます。
また、住宅ローンを返済することを条件に家を配偶者にプレゼントした場合、プレゼントした側にも所得税や住民税がかかる可能性があります。 これは、住宅ローンの金額分で家をお金と引き換えに譲ったとみなされ、プレゼントした人が住宅ローン分の利益を得たと見られるからです。 「おしどり贈与」が使えるかどうか不安なときは、早めに税理士さんに相談することをおすすめします。
まとめ
「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)は、残された配偶者に「これからも安心して自宅に住み続けてほしい」という願いを叶えることができる、とても良い制度です。
でも、もし相続税を安くすることだけを考えて「おしどり贈与」を検討するなら、贈与にかかる費用や、相続の時に使える他の特例も一緒に考えてみることが大切です。 場合によっては、費用などを考えると、税金がほとんど安くならないこともあります。
家をプレゼントするというのは、大きなお金が動くことですし、手続きも少し複雑です。 だから、税理士さんや司法書士さんといった専門家に相談しながら、慎重に進めていくのが一番安心ですよ。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
電話 0120-003-396
お問合せ受付時間 平日9時から18時
名古屋市の税理士法人アイフロント
名古屋オフィス – 名古屋市北区の税理士事務所 |税理士法人アイフロント (ai-front.com)