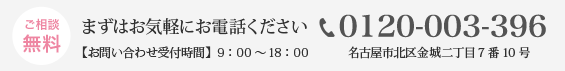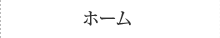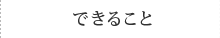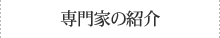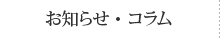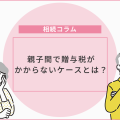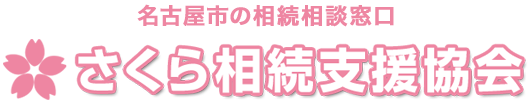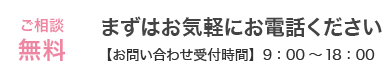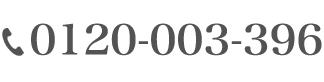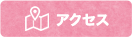おじいちゃんやおばあちゃんが老人ホームで亡くなった時の「相続税」ってどうなるの?
更新日:2025.08.23
Contents
はじめに
もし、おじいちゃんやおばあちゃんが老人ホームに住んでいて、そこで亡くなった場合、財産を受け継ぐ時に「相続税」という税金がかかることがあります。この時、いくつか気をつけなきゃいけないポイントがあるんだ。
特に大事なのが、「小規模宅地等(しょうきぼたくちとう)の特例」っていう、土地の税金をグッと安くできるお得な制度!「老人ホームに住んでたら、もう元の家には住んでないから、この特例は使えないのかな?」って思うかもしれないけど、実は使える場合もあるんだよ。
この記事では、老人ホームにいた人が亡くなった時の相続税の手続きや、このお得な特例について、分かりやすく解説していくね!
老人ホームで亡くなった人の相続税、どこに申告するの?
まず、相続税の申告は、亡くなった人(「被相続人(ひそうくしょくじん)」といいます)が老人ホームに入っていた住所を管轄する税務署に出します。
「住民票があった住所」とか、「相続する人が住んでいる住所」と間違えやすいから気を付けてね!どこの税務署に出せばいいか分からない時は、国税庁のホームページで郵便番号や住所、地図から調べることができるよ。
老人ホームに住んでた人の家にも「小規模宅地等の特例」は使えるの?
「小規模宅地等の特例」っていうのは、亡くなった人が住んでいたり、お店をしていたりした土地の税金評価額を、ある条件を満たせば最大80%も安くできるっていう、とってもお得な制度なんだ。
この特例を使うには、亡くなった人が、亡くなる直前までその土地に住んでいたことが条件になることが多いんだ。
じゃあ、老人ホームで亡くなった場合は、この特例は使えないのかな?
結論から言うと、いくつかの条件を満たせば、使うことができるんです!ここでは、亡くなった人が住んでいた家(「特定居住用宅地等(とくていきょじゅうようたくちとう)」といいます)について説明するね。
「小規模宅地等の特例」が使える条件
老人ホームで亡くなった方の元の自宅の土地に「小規模宅地等の特例」を使うには、まず、亡くなった人自身が次の2つの条件をクリアしている必要があります。
- 亡くなる直前に、「要介護認定(ようかいごにんてい)」などの介護が必要な状態だと認められていたこと。
- 国が定めている「特別養護老人ホーム」などの特定の老人ホームに入っていたこと。
これらの条件を満たしていれば、たとえ亡くなる直前に元の自宅に住んでいなかったとしても、「小規模宅地等の特例」の対象になるんだ。
相続する人ごとの条件
土地が「小規模宅地等の特例」の対象になることが分かったら、次は相続する人(財産を受け継ぐ人)が条件を満たしているか確認します。相続する人によって条件が違うから見てみよう!
- 亡くなった人の配偶者(夫や妻)
- この特例を使うための条件はありません。一番優先されます。
- 亡くなった人と一緒に住んでいた親族(家族)
- 次の2つの条件をどちらも満たさないといけません。
- 亡くなる直前から、相続税の申告期限まで、その家(土地)に住み続けていること。
- その土地を、亡くなった時から相続税の申告期限まで所有していること。 住民票だけを移して、実際には住んでいない場合は、この特例は使えません。
- 上記1、2以外の親族(同居していない家族など)
- 次の6つの条件をすべて満たす必要があります。これはちょっと厳しい条件だよ。
- 日本の国籍があること。
- 亡くなった人に、配偶者がいないこと。
- 亡くなる直前に、その家(土地)に住んでいる相続人がいないこと。
- その土地を受け継いだ親族が、過去3年以内に、自分や自分の配偶者(夫や妻)など(親族や、親戚が経営する会社が持っている家など)が所有する家に住んだことがないこと。
- その土地を受け継いだ親族が、相続が始まった時に、自分が住んでいた家を、これまでに一度も持ったことがないこと。
- その土地を、相続が始まった時から相続税の申告期限まで所有していること。
つまり、亡くなった人に配偶者がいなくて、一緒に住んでいた親族もいない場合に、今まで自分の家を持ったことがなく、さらに配偶者や親族が持っている家にも住んだことがない相続人であれば、たとえ同居していなくても、「小規模宅地等の特例」が使える可能性があるということになります。かなり限られたケースだね。
「小規模宅地等の特例」を使う時に気をつけたいこと
「介護が必要な状態の申請中」に亡くなった場合
老人ホームに入っていた人の自宅の土地に「小規模宅地等の特例」を使うには、亡くなった人が「要介護認定」などを受けていないといけないって話をしたよね。じゃあ、「要介護認定を申請中に亡くなっちゃった場合はどうなるの?」って思うかもしれない。
この場合、一見すると特例は使えないように思えるよね。でも、実は、亡くなった後に「要介護認定」が認められたら、この特例が使えるんです!
なんでかというと、要介護認定の効果は、申請した日(亡くなる前)までさかのぼって適用されるからなんだ。つまり、亡くなる前に申請していて、亡くなった後に認定された場合は、「生前に認定されていた」ことになり、特例の条件を満たすことになるんです。亡くなった時にまだ認定が出ていなくても、特例をあきらめないで確認してみましょう。
特例の割引率が減ったり、使えなくなったりするケース
次のような場合だと、「小規模宅地等の特例」の割引率が下がったり、全く使えなくなったりすることがあるから、注意が必要です。
- 老人ホームに入ってから家を貸し出した場合
- もし、亡くなった人が老人ホームに入ってから、元の家を誰かに貸し出していた場合、その土地は「貸付事業用宅地等(かしつけじぎょうようたくちとう)」という種類になります。この場合も「小規模宅地等の特例」は使えるんだけど、割引率が小さくなるんだ。具体的には、「貸付事業用宅地等」の割引は、200平方メートルまでで50%しか減額されません。一方で、亡くなった人が住んでいた土地の場合は、330平方メートルまでで80%も減額できるので、割引される金額が大きく変わってきます。家を貸すことで得られるお金(家賃収入)と、税金が安くなる分を比べて、貸し出すかどうかを判断する必要があります。
- 二世帯住宅で「区分所有登記(くぶんしょゆうとうき)」をしていた場合
- 例えば、1階はおじいちゃん、2階は子ども名義、という風に、それぞれの部分を別の人が所有しているという登記(区分所有登記)をしている二世帯住宅の場合を考えてみましょう。この場合、子どもの相続する部分には「小規模宅地等の特例」は使えません。なぜなら、子どもは自分の家(2階)に住んでいて、亡くなった人(おじいちゃん)と同居していた親族とはみなされないからです。こうなるのを避けるには、生前に「区分所有登記」をやめて、家全体を誰か一人の名義にしておく必要があります。でも、この手続きには、また別の税金(贈与税や所得税)がかかわってくる可能性があるので、税理士さんに相談するのが良いでしょう。
老人ホームの「入居一時金」が戻ってきたらどうなるの?
老人ホームによっては、最初にお金(「入居一時金」といいます)をまとめて払う場合があります。これは、毎月の利用料を前払いするようなもので、少しずつ使われていきます。もし、この入居一時金が全部使われる前に亡くなった場合、残った分のお金が返ってくることがあります。この返ってきたお金が、誰が払ったお金だったかによって、相続税の扱いが変わってくるから見てみよう!
亡くなった人自身が払っていた場合
もし入居一時金を亡くなった人自身が払っていた場合は、返ってきたお金も、亡くなった人の財産になります。なので、他の財産と合わせて相続税の計算をする必要があります。
夫婦で入居していて、亡くなった人が払っていた場合
夫婦で老人ホームに入っていて、入居一時金を亡くなった人(例えば夫)が全部払っていた場合、入居を続ける配偶者(妻)の残っている入居一時金も、亡くなった人の財産として計算に入れます。亡くなった時点で、配偶者の入居一時金の残額が対象になります。
もし、契約上、配偶者の残っている入居一時金を、亡くなった人が返してもらう権利がない場合は、亡くなった人から配偶者への「贈与(プレゼント)」とみなされて、贈与税がかかる可能性があります。
入居一時金が「贈与」とみなされる可能性も
例えば、夫が妻の老人ホームの入居一時金を払ってあげた場合、「これは夫から妻へのプレゼント(贈与)になるの?」という疑問が出てきますよね。
この時のポイントは、「普通の生活費として必要な範囲かどうか」です。夫婦には、お互いに助け合って生活する義務があって、生活費に使うための、普通の範囲内のプレゼント(贈与)は税金がかからないことになっています。
だから、入居一時金がこの「普通の生活費」の範囲内だと認められるかどうかが、税金がかかるかどうかの判断基準になるんです。どこまでが「普通の生活費」になるかは、老人ホームに入った目的や、施設の設備などを総合的に考えて判断されます。過去には、1億円以上の入居一時金が「贈与だ」と判断された例もあるので、入居一時金が数千万円以上と高額な場合は、注意が必要だと言えるでしょう。
老人ホームの未払いのお金は、相続財産から引ける!
もし、亡くなった人が老人ホームに払うべきお金が残っていて、それを相続する人が亡くなった後に払った場合は、相続財産からその分を差し引くことができます。これを「債務控除(さいむこうじょ)」と言います。領収書などをしっかり保管しておきましょうね。
老人ホームの費用の一部は「医療費控除」にできるかも!
老人ホームの費用の一部は、「医療費控除(いりょうひこうじょ)」という制度を使って、税金が安くなることがあります。医療費控除の対象になる項目や金額は、施設のタイプによって決められています。
施設からもらう領収書には、基本的に対象となる金額が書いてあるので、確認してみてください。亡くなった人が生前に払っていた費用は、亡くなった後にする「準確定申告(じゅんかくしんこう)」という手続きで税金が安くなります。もし亡くなった人と一緒に暮らしていた家族が払った場合は、その家族の確定申告で税金が安くなります。
「準確定申告」の期限は、亡くなったことを知った日の次の日から4か月以内と、普通の確定申告とは違うので注意してくださいね。
さいごに
おじいちゃんやおばあちゃんが老人ホームで亡くなった場合の相続税の手続きについて説明しました。相続税の申告は、老人ホームの住所を管轄する税務署に出すんだよ。
老人ホームに入っていた場合でも、土地の税金評価額を大きく安くできる「小規模宅地等の特例」は使える可能性があります。でも、使える条件が細かく決められているから、そもそも特例の対象になるのかどうか、しっかり確認しましょう。
また、老人ホームならではの「入居一時金」の扱いもあるので、相続税の計算で少しでも不安があるときは、税理士さんに相談することが大切です。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
電話 0120-003-396
お問合せ受付時間 平日9時から18時
名古屋市の税理士法人アイフロント
名古屋オフィス – 名古屋市北区の税理士事務所 |税理士法人アイフロント (ai-front.com)