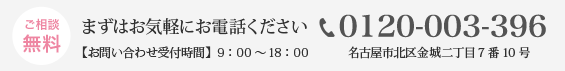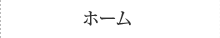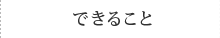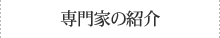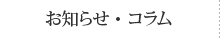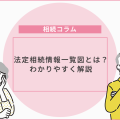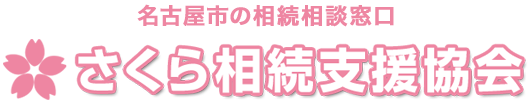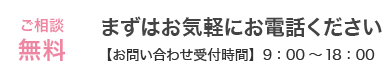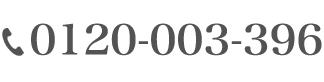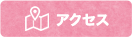連絡がとれない相続人がいる、さてどうする?について解説
更新日:2025.05.13
Contents
はじめに
相続手続きが進まない原因の一つに、連絡が取れない相続人の存在があります。遺産分割を協議で決定するには、相続人全員の同意が必要です。ひとりでも連絡がつかない相続人がいると、手続きが進まず、相続税の特例や優遇措置を受けられません。また、遺産の活用や処分にも支障が生じ、後々トラブルになる可能性もあります。本記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について、具体的に解説します。
連絡がとれない相続人がいるとどうなるのか
相続人の中に連絡が取れない人や、相続手続きに非協力的な人がいると次のような問題が生じます。
◇ 遺産分割協議ができない
◇ 相続税の特例が受けられない
◇ 遺産の活用や処分ができない
これらがどう問題となのか、それぞれみていきましょう。
遺産分割協議ができない
遺産分割協議とは、相続人同士が話し合ってそれぞれの遺産相続割合を決めることをいいます。相続の割合は法律で決まっているのでは?と思う方もいらっしゃると思いますが、法律で示されているのはあくまでも目安です。また、その目安通りに相続するとしても、どの遺産を分けるのかは話し合いで決める必要があるでしょう。
遺産分割協議は、最終的に遺産分割協議書という書面を作成することになります。この書面には相続人全員の署名と押印がなければ法的にその効果を認められません。そのため、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないのです。つまり、相続人の中に連絡が取れない人や、非協力的な人がいると遺産分割協議ができません。
相続税の特例が受けられない
遺産分割協議ができず分割割合が決定していなくても、相続税の申告が必要な場合は期限内に申告と納税を行わなければなりません。相続税の申告期限は、相続人となったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割ができていないときは、法定相続分の割合で計算し、申告納税を行うことになります。このとき、相続税の負担を軽くできる小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度は利用できません。これらの特例は、遺産分割協議によって分割がされていることが条件であるためです。小規模宅地等の特例が利用できれば、土地の評価額を最大8割減額できますし、配偶者控除が適用できれば配偶者が相続する遺産は最低1億6千万円まで非課税になります。このように遺産分割協議ができないことのデメリットは、非常に大きいと言えるでしょう。
遺産の活用や処分ができない
相続税の申告が不要な場合は、連絡がとれない相続人を放置していてもいいのではないかと思われるかもしれません。もし亡くなった人に何も遺産がなければ、そのままでも大きな問題にはならないでしょう。しかし、亡くなった被相続人が、銀行に預金をしていたり不動産を所有していたりした場合は、そのままにしておくとトラブルになる可能性があります。特に不動産は注意が必要です。
不動産を相続した人は、法務局で登記を行わなければなりません。これを相続登記といい、2024年4月1日から義務化されました。相続登記を怠ると10万円以下の過料が科されます。相続登記を行う際には、遺言書または遺産分割協議書が必要です。これは、遺産分割について相続人同士で争いがなかったとしても、変わりません。ただし、遺産分割協議書がなくても相続登記ができる場合があります。それは、法定相続割合に応じて相続人が不動産を共有取得するときです。つまり、1つの不動産を複数の相続人で分割して権利保有することになります。この場合、遺産分割協議書は不要となるので、連絡がとれない相続人がいても問題ありません。しかし、共有された不動産は売却したり賃貸したりする際に共有者全員の同意が必要となるなど、その後の活用がしづらくなります。さらに、持ち分については他の共有者の同意なく売却できるため、知らないうちに全く関係のない人が共有者になっていたということも起こり得るのです。共有状態のまま長年放置すると権利関係が複雑になり、次に相続する家族も大変な思いをすることになります。そのような状態にならないためにも、しっかり分割を行い登記することが大切です。
また、被相続人の預金を引き出す際にも、遺産分割協議書が必要です。入院費の清算や葬儀費用に充てるため、被相続人の口座から一定の預金を引き出せる制度があります。ただし、金額に制限が設けられています。預金残高が低額または0円である以外は、やはり遺産分割協議書は必要となるでしょう。
住所などはわかっているが連絡がとれない場合
相続人の住所や連絡先はわかっているが、連絡が取れない場合の対処法から考えていきます。
相続手続きが必要な旨を手紙で伝える
住所やメールアドレス、電話番号などがわかっている場合は、まずは相続手続きが必要だということを伝えましょう。長年疎遠であれば、相続が生じたことを知らないかもしれません。また、相続手続きについて詳しい人は少ないので、丁寧に説明することも必要です。それでも相手方から反応が得られなければ、このままでは調停になる可能性があることも伝えるべきでしょう。
遺産分割調停を申し立てる
手紙やメールを出しても相続人から連絡がないときは、家庭裁判所の力を借りましょう。遺産分割調停とは、裁判とは異なり、家事審判官(裁判官)と調停委員からなる調停委員会と一緒に行う話し合いです。当人同士では話し合いが進まない場合に、中立な立場の人が間に入り解決を促します。遺産分割調停は相手方(連絡がとれない相続人)の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てが必要です。
申立てがなされると、家庭裁判所から相手方に通知が出されます。裁判所からの手紙なので、連絡を無視していた相続人も事の重大さを理解してくれるかもしれません。
調停に参加しないと遺産分割審判に移行する
遺産分割調停の呼び出しがあっても応じない人がいると、調停が行えません。調停はあくまでも話し合いの場なので、当事者が集まらなければ不成立となります。
調停でまとまらない場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。遺産分割審判は、通常の裁判のように裁判官が当事者の主張や資料に基づいて決定する手続きです。相続人が出頭しなくても、遺産分割の方法が決定します。裁判官の判断によるため、必ずしも当事者の希望どおりの分割になるとはかぎりません。審判の決定に従わない場合は、強制執行が行われる可能性もあります。
連絡先や住所が一切わからない相続人の場合
長年疎遠であったり会ったことがなかったりする相続人がいる場合、連絡先や住所が一切わからないこともあります。そうしたときの対処法についてみていきましょう。
「戸籍謄本」「戸籍の附票」から住所を調べる
まずは、「戸籍謄本」と「戸籍の附票」から住所を調べます。
戸籍謄本とは、同じ戸籍内の全員の身分事項について記載されているものです。他方、戸籍の附票とは、住民票の移り変わりを記録したものになります。戸籍の附票は本籍地の役所に請求しなければなりません。相続人の調査時に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得していれば、そこから相続人の本籍地が調べられます。
請求する人が配偶者や直系血族以外の場合、それらの方からの委任状や相続人であることの証明が必要となる点に注意が必要です。また、2024年3月から戸籍謄本等の広域交付制度が開始し、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本が請求できるようになりました。ただし、戸籍の附票についてはこの広域交付を利用できないため、本籍地の役所に請求しなければなりません。
不在者財産管理人の選任を申し立てる
相続人の住民登録上の住所がわかっても、そこに居住していない場合はさらなる調査は困難になります。この場合、不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。不在者財産管理人とはなにか、どのように申し立てるのかについて以下でみていきましょう。
不在者財産管理人とは
行方不明となっている人の財産を公正に管理するための制度が、不在者財産管理制度です。不在者財産管理人は裁判所によって選任され、通常は弁護士や司法書士といった専門家がなります。ただし、財産管理人となるために資格は必要ではなく、不在者との関係や利害関係の有無などを裁判所が考慮して決定されます。
不在者財産管理人が行えること
不在者財産管理人の主な職務は、不在者の財産を管理保全することです。財産管理人を監督するのは裁判所であるため、権限外行為を行う場合は裁判所からの許可が必要となります。遺産分割協議は不在者の財産を管理保全する業務ではないため、裁判所から「権限外行為許可」という手続きを経なければなりません。
財産管理人の職務は不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者が亡くなったとき、不在者の財産がなくなったときまで継続されます。財産管理人に支払われる報酬は不在者の財産から支払われますが、不足する場合は、申し立て人が相当額を予納金として納付しなければなりません。
申立てに必要な書類
不在者財産管理人の申し立てには、次の書類が必要です。
(1)申立書
(2)標準的な申立添付書類
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 不在の事実を証する資料
- 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等)
申立てに必要な費用は収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手になります。切手の金額については申し立てる裁判所に確認が必要です。
失踪宣告を行う
生死不明の状況が7年以上経過しているときは、失踪宣告が可能です。失踪宣告が行われると、その人は死亡したと同様の扱いがされることになります。失踪宣告には普通失踪と危難失踪の2つがありますが、戦地に臨んだり、海で行方不明になったりと危険に遭遇して行方不明になった場合以外は、普通失踪での申し立てが一般的です。危難失踪の場合は、危機が去ってから1年で失踪宣告の申し立てが可能ですが、普通失踪では生死不明となってから7年が経過していなければなりません。
失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したという扱いになるので、その相続人が参加しなくても遺産分割協議が行えます。ただし、失踪宣告を受けた人に相続人がいる場合は、その相続人を遺産分割協議に参加させなければなりません。
遺言書があれば遺産分割協議は不要
被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議は不要となります。遺産分割協議書の提出が求められる手続きについても、遺言書を示すことで分割について証明が可能です。相続人に連絡が取りにくい人がいる場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
さいごに
連絡がとれない相続人がいる場合の対処法について説明しました。
相続人が揃わないと、遺産分割協議ができません。遺産分割協議ができないと、相続税の特例や優遇を受けられず、相続税の負担が重くなる可能性もあります。その他、遺産の処分や活用もしにくくなどデメリットが多いといえるでしょう。連絡がとれない相続人とのやりとりを個人で行おうとすると、大変な時間と労力、精神的負担がかかりますので、専門家に依頼することも必要です。まだ相続が発生していない場合は、遺言書を作成するなど事前の対策も検討してください。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
電話 0120-003-396
お問合せ受付時間 平日9時から18時
名古屋市の税理士法人アイフロント
名古屋オフィス – 名古屋市北区の税理士事務所 |税理士法人アイフロント (ai-front.com)