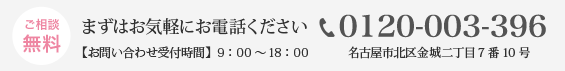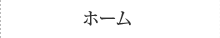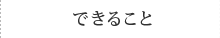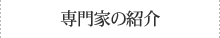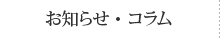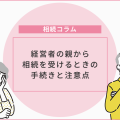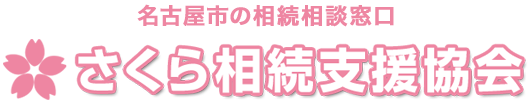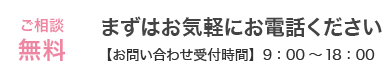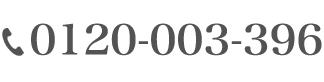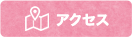法定相続情報一覧図とは? わかりやすく解説
更新日:2025.01.29
Contents
はじめに
相続で不動産や預金を引き継ぐと、名義変更などの手続きが必要です。名義変更の手続きでは、必要書類として戸籍・除籍謄本や住民票などを提出しなければなりません。これらの必要書類の収集を簡素化して、名義変更手続きを便利にするために生まれたのが、法定相続情報一覧図です。当初は不動産の相続登記のために新設されましたが、現在は銀行や保険の手続き、相続税の申告にも利用されています。ここでは、法定相続情報一覧図の作成方法や、メリットデメリットについて説明します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を図で示した書類です。被相続人を中心とした家系図と考えていただくとわかりやすいでしょう。これは、法定相続情報証明制度に基づいて行われるもので、相続によって取得した不動産の登記手続きを簡易にするために施行されました。制度開始直後は、不動産登記にのみ適用されていましたが、現在は金融機関での名義変更や相続税の申告、生命保険などの請求にも利用できるようになっています。
法定相続情報一覧図を取得するメリット
法定相続情報一覧図のメリットとしては、次の3点があげられます。
・各手続きに戸籍・除籍謄本の提出が不要になる
・名義変更などの手続きが同時に進められる
・各機関での確認時間が短縮できる
それぞれみていきましょう。
各手続きに戸籍・除籍謄本の提出が不要になる
相続によって取得した不動産や金融資産は、名義変更が必要です。このとき、相続での取得や被相続人との関係を証明するために、戸籍謄本や除籍謄本などの提出を求められます。しかし、相続情報一覧図があれば、戸籍・除籍謄本の提出は不要です。相続情報一覧図は、その内容を法務局が確認し証明しているため、他の書類は必要ありません。
名義変更などの手続きが同時に進められる
相続情報一覧図を使わずに相続手続きを行うと、戸籍謄本等の書類が返却されるまで他の財産の手続きができなくなります。戸籍謄本等を複数取得して進める方法もありますが、取得には費用や日数が余分にかかることに。他方、相続情報一覧図は無料で何枚でも取得できるので、複数枚請求しておけば、名義変更手続きの同時進行が可能です。
各機関での確認時間が短縮できる
通常、名義変更の申請を受けた機関は、戸籍・除籍謄本などから被相続人と申請者の関係を調べて、相続人であることを確認しなければなりません。しかし、相続情報一覧図があれば、法務局が被相続人との関係性を認証しているので、各機関が再度確認する必要がないのです。つまり各機関が確認に要する時間を節約でき、手続きが早く終わるでしょう。
法定相続情報一覧図のデメリット
反対に、法定相続情報一覧図のデメリットや利用できないケースは次のとおりです。
・相続情報一覧図を作成する手間がかかる
・相続放棄をした相続人がいる場合は利用できない
それぞれ説明します。
相続情報一覧図を作成する手間がかかる
相続情報一覧図は申請者が作成しなければなりません。法務局はあくまでも内容を確認し認証する役割のため、作成はしてくれないのです。つまり、必要な書類を一式集め、一覧図を作成する手間がかかります。名義変更などが必要な財産が少なければ、従来どおりの手続きの方が手間も時間も短縮できる可能性があるでしょう。
相続放棄をした相続人がいる場合は利用できない
相続人に相続放棄をした人がいる場合は、相続情報一覧図は利用できません。相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を1つにまとめたものであり、戸籍や住民票に記載されない内容は反映できません。相続放棄については戸籍などに載らないため、相続情報一覧図では分からず、名義変更などに利用できなくなります。
法定相続情報一覧図の取得方法
ここからは、具体的な法定相続情報一覧図の取得方法について説明します。
法定相続情報一覧図を取得できる人
法定相続情報一覧図を取得できる人(申出人となれる人)は、被相続人の相続人です。日本国籍がなく戸籍・除籍謄本を取得できない人は利用できません。また、申出人からの委任がある親族や弁護士・司法書士・税理士なども取得できます。
法定相続情報一覧図の発行申請先
法定相続情報一覧図の申出は、次のいずれかを管轄する登記所で行えます。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
窓口に行けない場合は、郵送での申出も可能です。
法定相続情報一覧図の取得にかかる費用
法定相続情報一覧図は無料で利用できます。再取得にも費用はかかりません。郵送で申出や再取得を依頼する際には、郵送料が別途かかります。また、戸籍・除籍謄本など必要書類の取得には所定の手数料が必要です。
法定相続情報一覧図の有効期限
法定相続情報一覧図は、登記所にて申出日の翌年から起算して5年間保管されます。その間は再交付の申請が何度も可能です。ただし、再交付の申出を行えるのは、最初の申出において「申出人」として氏名を記載した人のみとなります。そのほかの相続人は再交付の申出ができないので、「申出人」の委任を受けなければなりません。こうした事態を避けるために、最初の申出時点で「申出人」を連盟にしておく方法もあります。
法定相続情報一覧図作成から発行までの流れ
では、法定相続情報一覧図はどのように作成するのでしょうか。以下で説明していきます。
必要書類を用意する
まずは必要書類を用意しましょう。必要書類は下記のとおりです。
<必ず収集する書類>
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍・除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄(抄)本※被相続人が亡くなった日以後の取得であること
・申出人の身分証
<場合によって必要となる書類>
・各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
・委任状※親族に委任する場合は申出人と親族であることがわかる戸籍謄本など
・被相続人の戸籍の附票※被相続人の住民票の除票が市区町村で廃棄されて取得できない場合など
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍・除籍証明書が請求できるようになりました。ただし、住民票の除票はこの対象外ですので、被相続人の最後の住所地がある市区町村に請求しなければなりません。また、戸籍証明書等の広域交付は、配偶者・父母・子が請求でき、きょうだいは含まれないことにも注意が必要です。
法定相続情報一覧図を作成する
必要な書類が揃ったら、法定相続情報一覧図を作成しましょう。難しそうに思いますが、法務局のWebサイトにケース別の記載事例が載っていますので、これを見ながら作成できます。それでもご自身で作成するのが困難な場合は、司法書士や税理士に依頼することも可能です。
登記所へ申出を行う
法定相続情報一覧図が作成できたら、申出書と必要書類と一緒に管轄の登記所へ提出します。認証を受けて交付されるまでの期間は、特に不備がなければ1週間前後です。
法定相続情報一覧図作成時の留意点
法定相続情報一覧図を作成する際の留意点についてお伝えします。ポイントは3つです。
・続柄は戸籍と同じ表記にする
・相続放棄をした相続人も記載する
・相続人の住所記載は任意
続柄は戸籍と同じ表記にする
法定相続情報一覧図に記載する続柄は、戸籍の表記に揃えましょう。法定相続情報証明制度では妻を「配偶者」、長男を「子」と記載しても問題ありません。しかし、相続税の申告でこの一覧図を使用する際には、続柄が異なることで使えない場合があります。せっかく作成しても利用できないのではもったいないので、戸籍の表記に揃えておくことをおすすめします。
相続放棄をした相続人も記載する
法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を1つにまとめた書類なので、相続放棄をした相続人がいても、その人の情報を記載する必要があります。ただし、家庭裁判所によって推定相続人の廃除が決定した場合は記載しません。
相続人の住所記載は任意
法定相続情報一覧図への相続人の住所記載は任意です。住所を記載しない場合は、各相続人の住民票の写しも不要となります。記載しておくと、その後法定相続情報一覧図を利用した手続きの際に、各相続人の住民票の写しが不要となることもあります。住所を移す予定が当面ない場合は、住所を記載しておくのもいいでしょう。
まとめ
法定相続情報一覧図について解説しました。この制度を利用すると、戸籍や住民票の情報を1つにまとめられ、複数の相続手続きを同時に進められます。他方、一覧図を作成する手間がかかるため、名義変更が必要な遺産が少ないケースではあまりメリットを受けられないかもしれません。もともとは不動産の相続登記手続きを便利にするための制度なので、遺産に不動産が多い方はこの制度を利用するのがおすすめです。ご自身で作成する時間を節約したい場合は、司法書士や税理士に依頼するといいでしょう。
********
名古屋市の相続相談なら【さくら相続支援協会】
また、税理士法人アイフロントでは相続のご相談(1時間程度)は無料で承ります。お気軽にお電話ください!
電話 0120-003-396
お問合せ受付時間 平日9時から18時
名古屋市の税理士法人アイフロント
名古屋オフィス – 名古屋市北区の税理士事務所 |税理士法人アイフロント (ai-front.com)